ミクロソリウムが黒くなったり枯れてしまったりする原因を解説していきます。シダ病ではないのに黒くなって上手く育てられないという方は必見の内容となっています。
ミクロソリウムとは

Microsorum
ミクロソリウムとはウラボシ科の植物で、低光量でも育つ陰性植物です。
基本的に丈夫な水草であり、育成が簡単なため初心者の入門水草としてもよく使用されています。
また、ミクロソリウムにはいろんな種類がありサイズや形等が異なるため、自分の好みやレイアウトに合わせて種類を選ぶことができます。
ミクロソリウムの種類
ミクロソリウムには上記のような種類等があり、葉が細かったり、葉先が枝分かれしていたりなど、それぞれ違った特徴があります。
どれも難易度は同程度で、中景に配置してミクロソリウムの茂みを作ってあげると自然感溢れる雰囲気になります。
葉が黒くなる4つの原因
- シダ病
- pHと硬度が高い
- 光量が強すぎる
- 食害
①シダ病
ミクロソリウムが黒くなる原因には、シダ系植物特有の”シダ病”があります。
シダ病には葉の一部が茶色や黒色になって枯れだし、徐々に他の葉へ広がっていく特徴がありますが、水中感染で他の水草に感染していくようなことはあまりないようです。
- 高水温(28度以上)
- 通水性が悪い
対策
- 冷却ファンで水温を下げる
- 水槽サイズや環境にあったフィルターを使用する
- 傷んだ葉を全てカットする
シダ病を疑った場合は上記記載の対策で環境を整え、ミクロソリウムの傷んだ葉を全て切り取って新しい芽が生えてくるのを待ちます。
1. 冷却ファンで水温を下げる
夏場はどうしても高温になりがちで、何の対策も行わずにいるとすぐ水温が30度以上になってしまい、シダ病発生のリスクが上がってしまいます。
そのため室温で管理できない場合は、水槽用の冷却ファンを使用して水温を下げるようにしましょう。
2.水槽サイズや環境にあったフィルターを使用する
通水性や水質をより良くするためには、”外部式フィルター”の使用をおすすめします。
外部式フィルターはフィルターの中でも特に濾過能力が高く、適度な水流を生み出してくれるため水草水槽と相性抜群になっています。
「外部式フィルターは種類が多くてどれを使って良いかわからない」という方は、水槽サイズごとのおすすめ外部式フィルター(エーハイム)を解説した下記記事をご参照ください。
3.傷んだ葉は全てカットする
水槽や通水性の問題を改善したら、ミクロソリウムのシダ病にかかって黒くなった葉を全てカットし、元気な新芽が出てくるの待ちます。
水温や通水性の問題が改善されていないのに葉を切り落としても、せっかく生えてきた新芽がまたシダ病にかかってしまう可能性があるため、必ず環境を整えてからカットするようにしましょう。
②pHと硬度が高い
- 硬度を上げる素材(石や砂利等)を使用している
- 換水に使用する水道水のpH・硬度が高い
葉が黒くなって上手く育たない原因には、”pH”と”硬度(GH)”の高さが関係している場合があります。
多くの水草は”弱酸性の軟水”を好むため、逆の”アルカリ性寄りの硬水”になってしまうと水草は枯れたり成長不良を起こしてしまいます。
硬度が上がるとpHが下がりにくくなってしまうため、硬度を上げる石を使っている場合には水質の管理が難しくなってしまいます。
シダ病の症状とは少し違う、あるいはシダ病の対策を行ったが全く改善されなかったという方は、pHや硬度が高くなってる可能性がありますので一度水質を測定してみましょう。
対策
- 水質を測定する
- 硬度を上げる素材を使わない
- 換水時はpH調整剤を使用する
- ソイルを使用する
シダ病ではなくpHと硬度の上昇によるミクロソリウムの不調を疑う場合、まずは水質を測定し、pHと硬度を上げている原因を解決していきましょう。
1.水質を測定する

| 水質 | 解説 | 理想数値※ |
| pH(水素イオン濃度) | 数値によって酸性~アルカリ性を示す | 6.0前後(弱酸性) |
| KH(炭酸塩硬度) | この数値が低いとpHが下がりやすい | 3°dh以下 |
| GH(総硬度) | 軟水・硬水の判断 | 3°dh以下(軟水) |
| NO2(亜硝酸塩) | 生体に有害な物質 | 0mg/Lに近い程良い |
| NO3(硝酸塩) | NO2が分解されたもので毒性は下がる | 0mg/Lに近い程良い |
| CL2(塩素) | 水道水に含まれており熱帯魚やバクテリアに有害 | 0mg/Lに近い程良い |
水質の測定方法は、水に1秒浸けるだけで複数の項目が確認できるテトラの試験紙がおすすめです。
測定した結果、pH・KH・GHの値が高い場合には水質が不調の原因だったと考えられ、適した水質に変えていく必要があります。
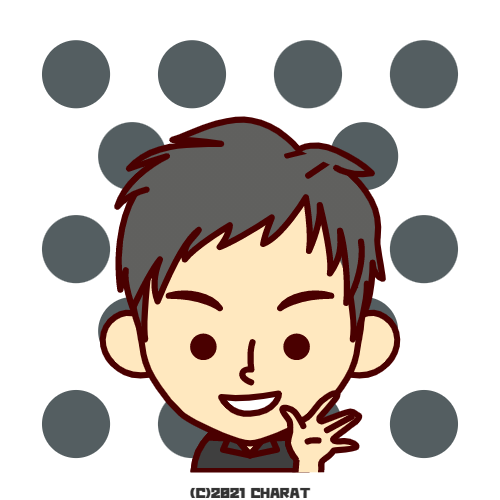
私の経験による基準ですが、GHは5°dh以上になってくると成長や見た目が悪く、8°dh以上も行けば黒くなったりしてまともに育つのはかなり難しい状態でした。下記の写真はGHが5.6°dhくらいにときのミクロソリウムで、ごわごわと縮れたように硬い感じの葉になっています。

2.硬度を上げる素材を使わない
pHや硬度を上昇させないためには、硬度を上げる石や砂利を使用しない事です。
レイアウトに硬度を上げる石等を使用していると水槽内の硬度が上昇し、pHが下がりにくくなるため、多くの水草が苦手な”アルカリ性寄りの硬水”になってしまいます。
少量の石等であれば、大きな影響はありませんが、石組み水槽のような大量の石を使う場合には水質への影響が大きくなってしまうため注意が必要です。
- 龍王石
- 青龍石
- 昇龍石
- 青華石 等
どうしても石組み水槽のように石をたくさん使ってレイアウトを組みたい場合には、上記の石は避け、水質への影響がかなり少ない”溶岩石”や”気孔石”を使用しましょう。
私も溶岩石を使用して石組み水槽を管理していますが、GHを4°dh以下にはキープでき、ミクロソリウムを含めた水草たちは良い状態を保てています。
3.換水時はpH調整剤を使用する
pHが高い水道水の地域では、換水時に”pH調整剤”を使用して行いましょう。
カルキ抜き剤と同じ要領で、使用する水道水に規定量を入れるだけで簡単にpHとKHを下げることができます。
4.ソイルを使用する
ソイルには栄養が多く含まれているだけではなく、pHを下げる効果等もあるため、水草水槽とは相性が抜群の存在です。
ソイルには”栄養系”と”吸着系”の2種類があり、水草を美しく育てるには”栄養系”がおすすめです。
使い始めはコケが生えやすくなりますが、水草の美しさや成長速度が全く違いますので、より状態の良い水草に育成したい場合には”栄養系”のソイルを使用すると良いです。
中でもおすすめなのが、”リベラソイル”と”アクアリウムソイル”です。
リベラソイル
- 窒素や微量元素など水草に必要な栄養がしっかり入っている
- ソイルが崩れにくく、通水性が高い
- 長期間に渡って水草が元気に育つ
- 多くの水草が好む弱酸性・軟水にする
- 栄養系の特徴であるアンモニアの発生が緩やか
リベラソイルは窒素や微量元素なども多く含み、長期間好調を維持しやすい栄養豊富なソイルです。
育つソイル
- 初期の濁りが少なく透明度が高い
- pHやGHを下げ、多くの水草が好む水質にする
- コケが生えにくい
- 水草がよく育つ
- ノーマルとパウダーの2種類がある
”育つソイル”はアクアテイラーズ社が出すオリジナルソイルのことで、吸着系ソイルなのに水草がよく育ち、赤系水草も鮮やかな赤色に成長させることができる優秀なソイルです。
③光量が強すぎる
強すぎる照明は、”成長阻害”や”葉焼け”を起こしてしまうことがあります。
葉焼けとは人間でいう火傷のようなもので、葉が茶~黒色に変色して枯れてしまいます。
葉焼けまではしなくても、強すぎる照明は成長阻害を起こしてしまいますので強すぎる照明には注意しましょう。
対策
- 照明と水草の距離を離す
- 水草育成に適した照明を使う
1.照明と水草の距離を離す
照明を吊り下げタイプの照明にすることで水槽との距離をコントロールしたり、水草自体を水槽の低い位置や流木等の影に植えたりすることで葉焼けを防ぐことができます。
アクロ TRIANGLE LED GROWであれば、”水草がよく育つ”・”コスパ最強”・”吊り下げ設置が可能”という3つの特徴があるためおすすめです。
2.水草育成に適した照明を使う
水草育成に適した照明を使用することで過剰な高光量環境を防ぎ、ミクロソリウムだけではなく他の水草たちも美しく育成することができます。
Chihiros LED WRGB2であればスマートフォンアプリで”調光”ができるため、水草に適した光を作り出す事できます。
また、水草を非常に鮮やかに照らすことができるRGB素子LEDチップを使用しており、水草もよく育つ性能のためおすすめです。
④食害
ミクロソリウムは基本的に丈夫な種類ではありますが、古くなったり傷んだりした葉があると、エビ等の生体に食べられて穴があいてしまうことがあります。
エビの数が多すぎたり、コケや餌が少なかったりする環境では、食料を求めて丈夫で硬いミクロソリウムの葉でも食べてしまいますので、観察しながら食害を受けていないか確認してみましょう。
対策
- エビ等を別水槽へ隔離する
- 沈下性の餌を与える
1.エビ等を別水槽へ隔離する
コケが少なく、エビ等の数が多すぎる場合は、別の水槽で飼育してあげましょう。
既存の飼育水を使えば、生体の負担を減らしてすぐに移動できます。
2. 沈下性の餌を与える
エビ等が葉を食べているの確認できた場合は、コケ等の食料が足りていない可能性がありますので、沈下性の人口餌を与えてあげましょう。
水草の不調には必ず原因がある
ミクロソリウムがうまく育たない場合は、”シダ病”か”pH・硬度の上昇”に原因がある可能性が高く、照明の光が強すぎる場合もあるため、水質・環境を見直す必要があります。
ミクロソリウムに限らず水草の不調には、水温・水質・栄養・光量等が関係し、必ず何かの原因がありますので、日頃の水槽観察と水質チェックし、水槽の環境を知ることが大切になります。
下記記事では水草の”白化”原因について解説していますが、水草の不調に共通する栄養バランスの重要性についても解説していますので、水草の育成について学びたい方はそちらも参考にしていただければと思います。
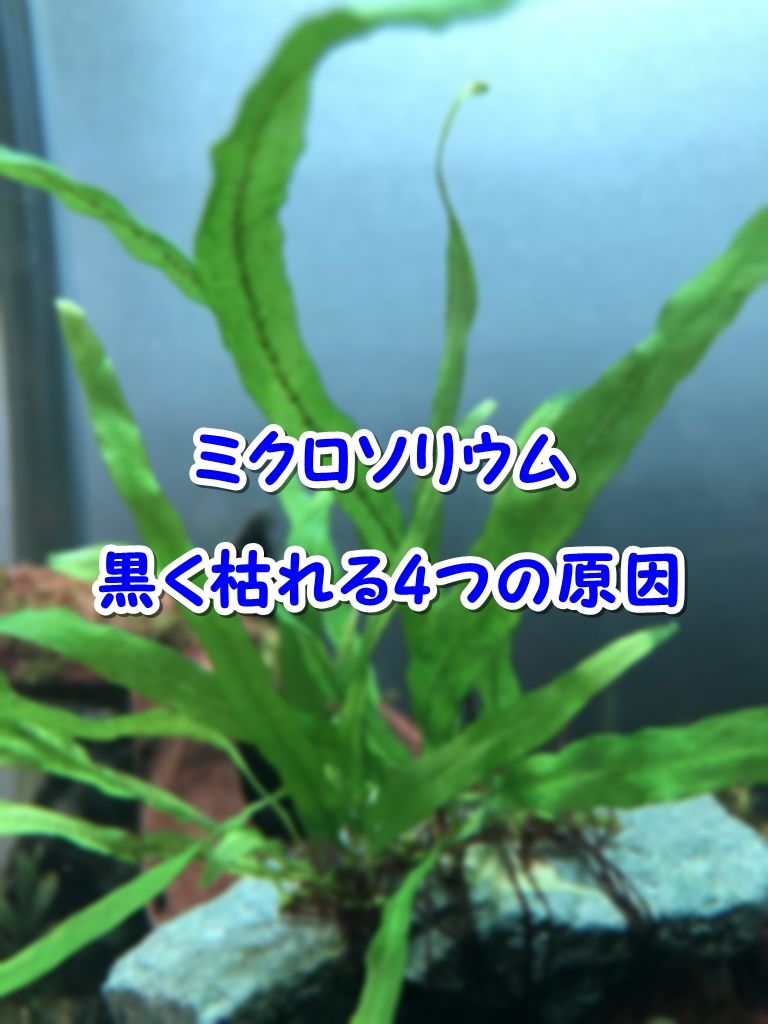
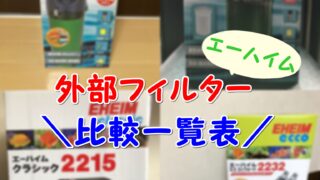
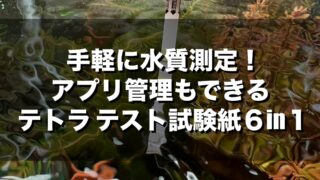
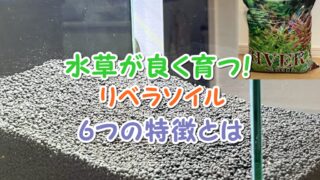
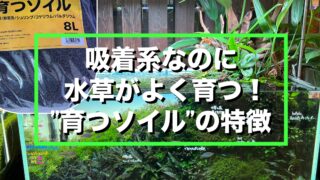
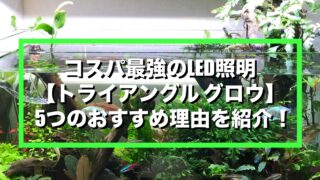

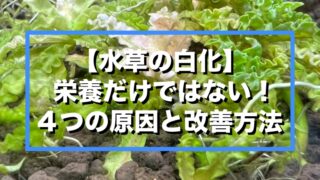



コメント